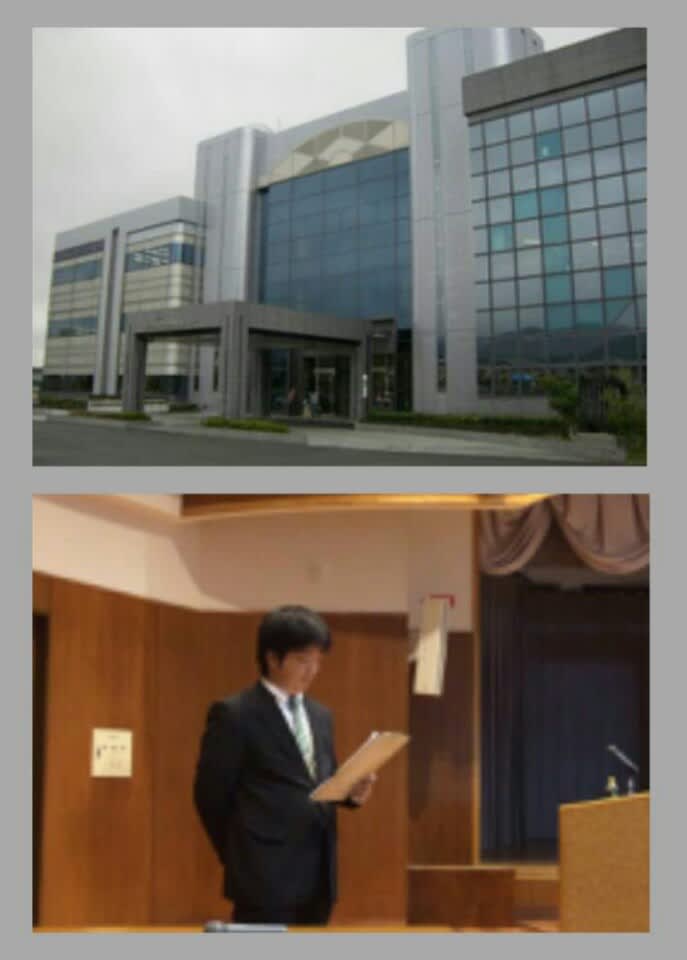
平成26年9月13日(土)、岩出市総合保健福祉センターで平成26年度 第1回 岩出市・紀の川市 介護関係職員合同研修会が行われました。
この研修は岩出市・紀の川市から委託を受け、和歌山県介護支援専門員協会 那賀支部が主催する研修会で、年2回開催されています。
私、谷所は和歌山県介護支援専門員協会 那賀支部の理事として司会を勤めさせていただきました。
今回の研修会の講師は那賀病院 管理栄養士 真珠文子さん。内容は「高齢者の栄養と嚥下について」。
参加申し込みの時点で178名と関心の高さをうかがわせました。
栄養管理は全ての治療の基盤であり、栄養状態が悪くては、治療効力を発揮できません。適切な栄養管理は予後を改善します。
エネルギーとたんぱく質が欠乏した状態を低栄養と言い、血液検査の結果(血清アルブミン値が3.5g/dl未満)や体重の減少等が重要な指標となります。
体重が6ヵ月間に5~8%減少すると、免疫機能の低下、筋力の低下、呼吸機能の低下、温度調節機能の低下、うつ状態といった低栄養の症状が見られるようになります。
摂食・嚥下障害の主な原因には、加齢や脳梗塞の後遺症、パーキンソン病等があります。
嚥下障害の徴候として、食事時間・食べ方の変化、食事内容・好みの変化、むせる、咳が出る、咽頭違和感・食物残留感、声の変化、痰の量の増加、食欲の低下、やせ・体重の変化等が挙げられます。
摂食・嚥下は先行期・認知期(何をどのように食べるかを判断する時期)、準備期・咀嚼期(食べ物を咀嚼し、食塊を形成する時期)、口腔期(食塊を口腔からのどに送り込む時期)、咽頭期(食塊を咽頭から食道へ送り込む時期)、食道期(食塊を食道から胃へ送り込む時期)の大きく5つの時期に分けて考えられており、どこに問題があるかで、対応が変わります。
その他、サルコペニアやリフィーディング症候群、病院・介護保険施設の嚥下食互換表や栄養サマリーの作成、嚥下食の調理実習といった那賀圏域医療と介護の連携推進協議会 病院・介護保険施設合同部会栄養チーム(病院8、介護保険施設13が参加)での取り組みについて、詳しく説明してくれました。
今後、介護が必要になっても、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるように、地域包括ケアシステムの構築が進められていきます。
真珠先生の話では、国は自宅を訪問し、支援できる管理栄養士を増やしていこうとしているそうです。
例えば、管理栄養士が調理であれば訪問介護(ヘルパー)、嚥下であれば言語聴覚士と連携を取ることで、より大きな効果を上げることができると思います。
管理栄養士が利用者様を支えるチームに加わることは、様々な面でプラスになるのではないでしょうか。
投稿者:居宅介護支援事業所 所長・谷所
[補足]
サルコペニア
加齢に伴う筋力の低下、または老化に伴う筋肉量の減少を指します。高齢者の転倒、骨折に繋がるだけでなく、虚弱に直接関与しており、生命予後のみならず、身体機能障害、要介護状態の大きな要因として理解されています。サルコペニアの原因は加齢のみの原発性と、活動、栄養、疾患による二次性に分類できます。
リフィーディング症候群
飢餓または重度の栄養不良の状態にある患者様、摂食前に重度の体重減少があった患者様、悪液質または消耗症の患者様に対して栄養補給を再開すると、水・電解質分布の異常により心不全・呼吸不全等の症状が起こり、最悪の場合には死に至ることもある代謝性合併症をいいます。
低リン血症・低カリウム血症・マグネシウム欠乏等の代謝異常、またインスリンの分泌異常により高血糖・低血糖を引き起こすことがある。
重度の栄養不良の状態にある患者様は食物摂取を開始する前に血清電解質濃度を評価・修正し、熱量の増加はゆっくりと行い、その際に微量栄養素必要量の100%以上のビタミン、ミネラルを補充する必要があります。